葬儀とは別に知人や友人を招いて、故人を偲ぶための機会を設けることをお別れ会・偲ぶ会と呼びます。
近年は葬儀そのものが家族葬・火葬式(直葬)などと縮小傾向にあります。
葬儀を簡易的に済ませる代わりに、お別れ会・偲ぶ会を開催すうる需要も増えています。
葬儀のように慌ただしく終える儀礼よりも、しっかりと予定を立てて開催される偲ぶ会の方が、生前の知人・友人も集まりやすいですし、故人との思い出に浸る余裕をもつことができます。
葬儀と合わせて計画することもありますが、中にはお別れ会をプロデュースする専門のサービスもあります。
お別れ会・偲ぶ会の無料相談:Story(ストーリー)
お別れ会・偲ぶ会が詳しくどのようなものなのか、開催するためにはどのような手順を踏むのかをこのページでまとめています。
葬儀とお別れ会・偲ぶ会の違い
お別れ会のプロデュースサービスを運営する鎌倉新書が実施した終活に関する実地調査において、4人に1人(25.4%)が「お別れ会に興味がある」と回答しています。
また、自分自身のお別れ会より、家族や知人友人のために開催したいと考える人が多いという結果が出ています。
現状はまだお別れ会を開催する人の割合は多くありません。
しかし、葬儀の簡素化が進んでいる現代では、その代わりに故人を偲ぶためのお別れ会を開催する需要が高まる可能性も考えられます。
社葬・団体葬もお別れ会の一つの形
社葬や団体葬という言葉もありますが、これらもお別れ会・偲ぶ会と同じ立ち位置のものです。
近親者のみで行われる葬儀とは別に、生前の知人が集まって故人を偲ぶための機会です。
葬儀と異なり、宗教的な儀礼は関係ない
お別れ会・偲ぶ会が葬儀と異なるのは、宗教的な儀礼に縛られない点が大きいでしょう。
葬儀では故人の宗教・宗派により、式の形式や段取りがある程度決められており自由度は少ないです。
お別れ会・偲ぶ会では宗教的な決まりとは関係なく、遺族や集まる知人の開催したいようにイベントを作ることができます。
お別れ会・偲ぶ会の形式
お別れ会はどのような形式で行うかは基本的に自由ですが、大まかに以下のような形式で執り行われるのが一般的です。
- セレモニー形式
- 会食パーティー形式
- セレモニー式と会食式の組み合わせ
葬儀・告別式に近い形のイメージがセレモニー式。
宗教的な儀礼にとらわれず、より自由度の高いものがパーティー式です。
結婚に例えるとわかりやすいかもしれません。
- 結婚式→葬儀・告別式
- 披露宴→お別れ会・偲ぶ会
結婚式はある程度形式張った流れをとりますが、披露宴は自由で独自な形で作られることがイメージできると思います。
直葬・火葬式と組み合わせるのが都合が良い
葬儀は故人が亡くなった直後に執り行われるので、慌ただしく終わってしまいます。
故人とゆっくりお別れができない、そもそも突然の葬儀には都合が合わず参列できないなどデメリットがたくさんあります。
それであれば、後日しっかり計画をした上でお別れ会・偲ぶ会を執り行ったほうが、参列者としてもありがたい場合が多いでしょう。
お別れ会・偲ぶ会を行うのであれば、無理して葬儀に知人を呼びつける必要も無くなります。
- 葬儀は親族で最低限の直葬・火葬式で済ませる
- お別れ会・偲ぶ会で知人・友人を招く
この組み合わせが、喪主としても参列者としても負担が少なくなり、なおかつ「ゆっくりお別れができなかった」「参列できなかった」という心残りも無くせるかもしれません。
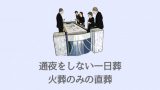
お別れ会・偲ぶ会の流れ/式次第
どのようなお別れ会を作るのかは自由ですし、特別な決まりはありません。
故人や遺族・参列者の希望のセレモニーを作ることができます。
あくまでも一例としてですが、一般的な式次第は以下のようになります。
- 係が集合開会の1時間前までに集まり、会の準備を行います
- 受付開会の1時間前を目安に参加者の受付を開始します
- 開会司会の進行のもと開会、開会の挨拶があります
- 式典黙祷、献奏、弔辞拝受、弔電拝読、お別れの会委員長挨拶、献花など
式典の内容・有無はお別れ会のプランによって異なります - 会食式典後に会食会場へ移動
献杯・会食の時間をとります
会食の内容・有無はお別れ会のプランによって異なります - 閉会
葬儀であれば基本的に葬儀社のスタッフのサポートのもと、喪主が進行を進めていきます。
しかし、お別れ会に関しては特別決まりはありませんので、それぞれの会に応じて司会の適任者を選ぶことができます。
お別れ会・偲ぶ会を開催する場所
お別れ会の会場は、その形式に応じて葬祭場やホテルで行われるのが一般的です。
式典を葬祭場で行ったのちに、ホテル会場へ移動してセレモニー・会食とすることもあります。
中には屋外やレストランでセレモニーを開催するお別れ会も存在します。
- 葬儀場
- ホテル
- レストラン
- 屋外
- 船上
- その他、故人の思い出の場所
会場が利用できるのであれば、葬儀のように場所の制限がなく、より自由なセレモニーを開催できます。
お別れ会・偲ぶ会を開催する時期やタイミング
開催時期に決まりはないが49日・一周忌に合わせることも
お別れ会の開催時期に決まりはありません。
葬儀後2週間〜2ヶ月ほどで行われるケースが多いようです。
また、49日や一周忌に合わせて行われることもあります。
葬儀と異なり、ある程度の準備期間を考慮して開催時期を決定すると良いでしょう。
準備期間は2ヶ月ほどかかる
お別れ会・偲ぶ会では準備期間が約2ヶ月ほど必要と言われます。
葬儀のように形式が決まっているものではありませんので、プランの計画から会場との調整などに日数が必要です。
セレモニープランの内容によって必要な準備期間も前後しますので、プランナーと相談の上で計画していきます。
お別れ会・偲ぶ会の準備
主に以下のような流れで計画していきます。
- 約2ヶ月前相談・打ち合わせお別れ会ができる業者(葬儀社や専門会社)に相談
葬儀の準備と合わせて、その後のお別れ会・偲ぶ会の相談をします
会場の選定や提案・見積もりを受けます - 葬儀・告別式家族葬・密葬・火葬式などを執り行う
- 約1ヶ月前詳細の計画を進める案内状の作成
プランの演出を決める
会場の調整
食事や返礼品の準備 - 約1週間前最終打ち合わせ参加者・人数が確定
進行表・席次の決定 - 当日事前準備・当日進行
お別れ会・偲ぶ会の開催費用/参加費用
開催費用
お別れ会・偲ぶ会はプランの内容・参加人数・会場の広さなどで費用が変動します。
大雑把ではありますが100万円〜300万円程度の幅に収まるようです。
このあたりは結婚披露宴にいくらかかるか?と同様に「内容による」という回答になります。
お別れ会の業者では見積もりまでは無料で受け付けているところが多いので、一度概算を出してみるのも良いでしょう。
参加者は会費制が多い
お別れ会の参加費用は会費制が多く、この場合は「香典辞退」となるのが通常です。
一人あたりの参加費は5000~20000円ほどの間で設定されます。
お別れ会・偲ぶ会を業者に依頼するメリット・デメリット
お別れ会は自身で企画しても良いですが、専門業者に依頼するのが通常でしょう。
- お別れ会にも対応している葬儀社
- お別れ会の専門業者
- セレモニー業者 など
お別れ会や偲ぶ会を開催するための経験がある人はとても少ないので、知見を持っている業者へ依頼したほうが無難です。
計画や準備でもかなり大変ですし、イベントごとは慣れている人でないと計画が失敗するリスクもあります。
葬儀社との打ち合わせの時点で、お別れ会の対応が可能か確認しても良いでしょう。
エンディング業界を全体的に担っている鎌倉新書では「Story(ストーリー)」というお別れ会のプロデュースを行っています。
お別れ会・偲ぶ会に関するマナー
お別れ会の服装
お別れ会では「平服でご参加ください」と案内されるのが一般的です。
喪服よりややカジュアルな、略喪服と言われる立ち位置の服装です。
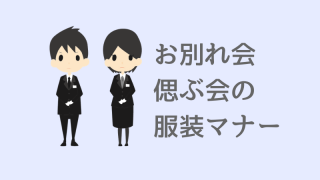
香典は1〜2万円ほど
お別れ会が会費制の場合は香典が不要です。
会費を徴収されない場合は、代わりに香典をお渡しする形です。
金額に決まりはありませんが、一般的には1〜2万円ほどとなります。

お別れ会・偲ぶ会まとめ
故人のため、遺族や生前の知人・友人のためにもお別れ会・偲ぶ会を検討してみましょう。
お別れ会・偲ぶ会の無料相談:Story(ストーリー)

