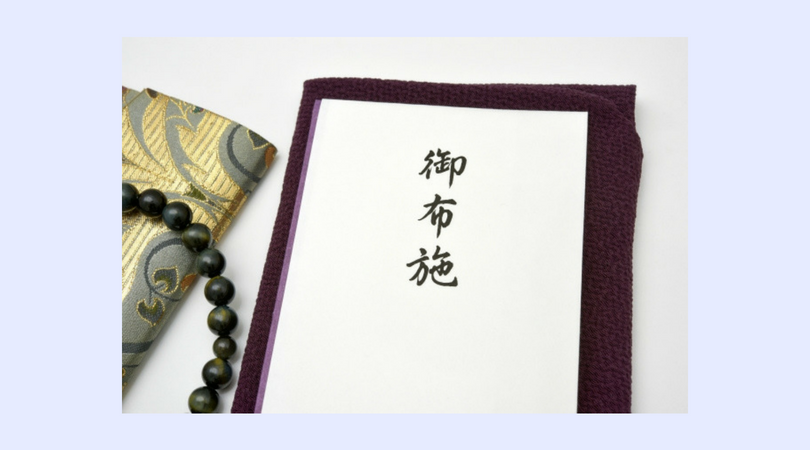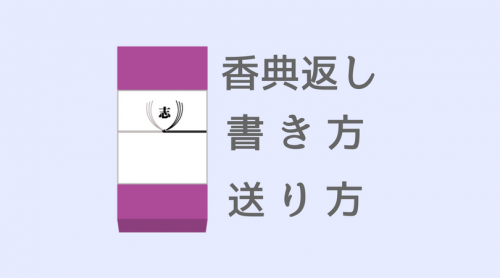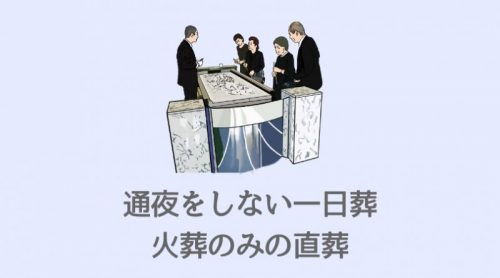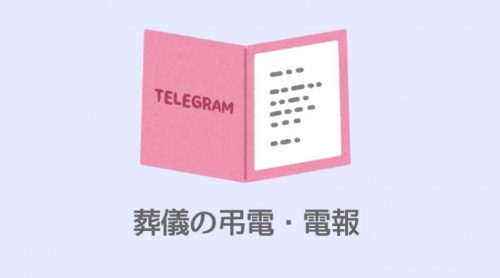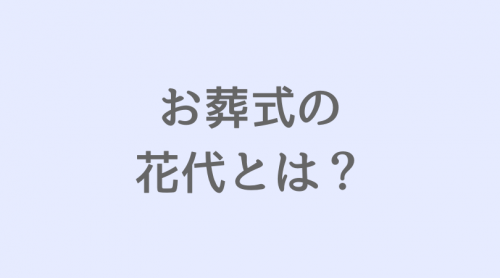お布施とは主に仏式の葬儀にて使われる言葉で、僧侶による読経や戒名を授けていただいたことに感謝し、お供えするものです。つまり、戒名料はお布施の内訳の一部であり、お車代・御膳代などもまとめてお布施とする場合もあります。
多くの方がお布施について疑問を持つ理由は、金額や書き方のマナーが明確に定められておらず、地域や寺院によって慣習が異なるためです。特に初めて喪主を務める方にとって、お布施の準備は不安の種となりがちです。この記事では、お布施の正しい書き方や相場金額、戒名料との違い、枕経のお布施についてなど、お寺や僧侶に失礼のないよう備えるために必要な知識を詳しく解説していきます。
お布施の書き方・包み方・渡し方
白封筒に包む方法
御布施の金額が分かったら、次に御布施を包む準備をしましょう。まずは何も書かれていない白い無地の封筒を準備します。専用のお布施袋がなくても、郵便番号の記入欄などがない白い封筒なら問題ありません。葬儀社が用意してくれる場合もありますので、確認しておくとよいでしょう。
お札を封筒に入れるときは、香典と違い裏向きにする必要がありません。また、香典では縁起を気にして割り切れない数字にすべきだと考える方もいますが、これは祝い事の場で言われている慣習なので、お布施には関係ありません。
表書き・中袋の書き方(縦書き基本編)
表書きは「お布施」「御布施」「御経料」などと縦書きで上段に書きます(何も書かない場合もあります)。下段には、施主の姓を「〇〇家」と書くか、もしくはフルネームで書きます(故人ではなく施主の名前です)。
中袋には喪主の住所と喪主の氏名を書きます。また、開けなくても金額が確認しやすいように、万が一金額を入れ間違えてしまわないように包んだ金額も記入しておけば手違いも防げます。
筆または筆ペンを使い、濃い墨で書きます(薄墨は香典で使うもので、お布施には濃い墨が適切です)。どうしても薄墨で書きたいというときは、葬儀社が貸してくれることもあるので遠慮せずに聞いてみましょう。
金額の書き方(漢数字と算用数字)
お布施の金額を記入する場合、伝統的には旧字体の漢数字(壱、弐、参、拾、阡、萬など)を用い、「金 〇〇圓也」(または「金 〇〇円也」)と表記します。例えば3万円なら「金 参萬圓也」となります。
ただし、近年では算用数字を使って「¥30,000-」と記入する方法も許容されています。地域や寺院によって異なりますので、不安な場合は葬儀社や菩提寺に確認するとよいでしょう。
横書きでの書き方について
お布施袋の書き方は、縦書きが基本とされています。しかし、算用数字を使用する場合など、横書きで金額を記入することもあります。その場合、封筒の表には「御布施」と縦書きし、金額を裏面に横書きで記入するパターンが一般的です。
横書きの場合の金額記入例:
- 「¥30,000-」
- 「¥30,000」
- 「30,000円」
特別な理由がない限り、伝統的な慣習に沿って縦書きで書くのが無難です。
渡し方とタイミング
お布施を渡すタイミングは、葬儀の前後でご挨拶と一緒に持っていくのが一般的です。ただ渡すのではなくあいさつとともに添えてお渡しします。
挨拶の例:
- 葬儀の前:「本日はよろしくお願い致します」
- 終了後:「本日はお世話になりました」「ありがとうございました」
この時は必ず小さいお盆か袱紗(ふくさ)の上に乗せて渡します。直接手で渡したり、床において差し出すのは失礼にあたるのでやめましょう。
ここで理解してほしいのは、お布施は謝礼ではないということです。御布施とは葬儀を執り行い、個人を供養していただいたお礼を僧侶にお支払いするのではなく、ご本尊にお供えするものです。
「これは本日の御礼です」と言うと、本質を理解していないと気を悪くされてしまう方もいらっしゃるので注意しましょう。
お布施の相場金額
お布施は厳密には「料金」ではありませんので、明確に金額が決められているものではありません。お布施の内訳や、周囲の対応を見て問題なさそうな金額を判断していきます。
御布施の内訳
以下の項目をひとまとめにして、お布施と呼ばれます。
御布施の主な内訳:
- 読経料:葬儀・法要などで僧侶にお経を上げてもらう時に渡すお布施のこと。葬儀や火葬などいくつか渡すタイミングがあります。
- 戒名料:戒名(芳名、法号)を頂いたことに対して支払う料金です。戒名には位(ランク)があり、つけられる戒名によってお布施の額も変動します。
- お車料:寺以外の場所で葬儀を行う場合に交通費として必要になる場合があります。5千円〜2万円程度の範囲で包みます。
- 御膳料:僧侶が還骨法要後の会食に出席しない場合に、料理膳に代えて5千円〜2万円を包みます。
御布施の相場と金額の確認方法
お布施の平均金額
日本消費者協会が発表している御布施の全国平均は47万円(読経料・戒名料・お車代・御膳代)とされています。
また、関東地方における戒名の違いによるお布施相場の一例としては、以下のようなものがあります:
戒名ランク別の相場金額:
- 院居士・院大姉:100万円以上
- 居士・大姉:50万円前後
- 信士・信女:30万円前後
地域や宗派による金額の違い
お布施の金額は宗教や宗派、都道府県や地方によってさまざまであり一概に目安として示せるものではありません。
九州・北海道は相場が安く、そこから関東に近づくにつれて金額が高くなる傾向があり、この相場は全国どこでも同じというわけではありません。また、御布施の金額の相場は同じ地方でもお寺によって若干の差があることがほとんどです。
お布施の金額の調べ方
お世話になるお寺が菩提寺(ぼだいじ)で、付き合いが長いのであれば、過去にお葬式を挙げた経験のある親戚や同じお寺の檀家の方に聞いてみるのが一番確認しやすい方法です。
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々の墓があり葬礼・仏事を営む寺のこと。大きな金額をお支払いしているので、過去に経験があればだいたいの方が覚えていらっしゃいます。
もし親戚に聞いても分からなかった場合には、僧侶に直接聞くしかありません。「御布施はいくらお包みすれば良いでしょうか?」と聞かれると、相手の心理的にも答えづらい部分があるので「皆さん御布施はいくら位包んでこられますか?」と尋ねると答えてくれることがあります。
それでも分からなかった時には葬儀屋に聞いてみましょう。お寺ごとの相場を把握している場合もありますし、仮に把握していなくてもほとんどの葬儀屋が代わりに聞いてくださります。僧侶も葬儀屋になら具体的な金額を言いやすいようなので、どうしても金額がわからなかった際には葬儀屋さんを頼ってみましょう。
枕経のお布施について
枕経とは
枕経(まくらきょう、まくらぎょう)とは、故人の枕元で僧侶に読んでもらうお経のことです。本来は臨終間際にあげるものでしたが、近年は病院で亡くなる方が増えたため、ご遺体を自宅や安置所に搬送した後に行われるのが一般的です。
枕経は故人を仏様の弟子にし、成仏を願うための儀式とされています。宗派によって枕経の特徴や唱える経典は異なりますが、どの宗派でも故人の冥福を祈る大切な儀式として位置づけられています。
枕経のお布施の必要性と金額相場
基本的に、枕経単体でのお布施は不要とされています。枕経は葬儀の一連の儀式の一部と考えられており、通夜や葬儀・告別式などのお布施と合わせて、すべての儀式が終わった後にまとめて渡すのが一般的です。戒名をいただいた場合は、戒名料も一緒に包みます。
もし枕経のお布施を個別に渡す場合は、1万円から3万円程度が相場とされています。ただし、これは一般的な目安であり、寺院や地域によって異なる場合がありますので、不安な場合は葬儀社に確認するとよいでしょう。
お車代について
枕経単体のお布施は不要ですが、僧侶に足を運んでいただいた交通費として「お車代」は別途用意し、枕経が終わった当日にお渡しするのがマナーです。お車代の一般的な相場は:
- 近距離の場合: 5千円程度
- 中距離の場合: 7千円程度
- 遠距離の場合: 1万円程度
ただし、寺院からの距離によって金額は変動しますので、状況に応じて調整してください。なお、遺族側で送迎を手配した場合やタクシーを用意した場合は、お車代は不要です。お布施とは別に「お車代として」と伝えて手渡すことで、僧侶も受け取りやすくなります。
お布施のよくある質問
- お布施と戒名料の違いは?
-
お布施は僧侶への謝礼全般を指しますが、その中に戒名料が含まれます。戒名料は故人に授ける戒名(法名)に対するものであり、戒名のランク(院居士・院大姉、居士・大姉、信士・信女など)によって金額が異なります。
お布施は基本的に読経料も含む総合的なものであるのに対し、戒名料はあくまで戒名を授けることに対する感謝の気持ちとなります。実際の葬儀では、これらを分けずにひとまとめにしてお渡しするケースが多いです。
お布施と戒名料の区別が難しい理由:
- 寺院や地域によって慣習が異なる
- 明確な料金表が存在しないことが多い
- 菩提寺との関係性によって扱いが変わる
- お布施が払えない時は
-
どうしてもまとまった金額が用意できず、僧侶へお布施をお渡しすることができない時はどうするべきでしょうか?
もしも金額が足りない時には葬儀の後のお付き合いもあるので僧侶に相談しましょう。「分割でも良いですよ」と言ってくださったり、正直に準備できる金額を伝えれば、それで了承してくれるお寺もあるようです。
金額に不安がある場合の対応策:
- 事前に菩提寺や葬儀社に相談する
- 現在の経済状況を率直に伝える
- 必要最低限の儀式に絞ることを提案する
- 仏式以外の宗教にもお布施はあるの?
-
御布施という呼び方ではありませんが、仏式以外の宗教にもお礼としてお支払いするものがあります。
たとえばキリスト教であれば、白い封筒に御花料・献金・御礼という表書きで牧師または神父へお渡しします。この時はオルガンの奏者にもお渡しする必要があります。渡すタイミングは仏式と同様で問題ありません。
神道の場合は御祭祀料・御榊料・御礼と白い封筒に表書きしてお渡しするのが一般的。御車代や御膳代も必要に応じて添えましょう。仏式と同様に、神葬祭の始まる前か後にお渡ししましょう。
お布施の相場と書き方まとめ
お布施は僧侶への謝礼ではなく、ご本尊へのお供えという本来の意味を理解して渡すことが大切です。金額は地域や宗派、菩提寺との関係によって大きく異なるため、事前に確認することをおすすめします。
書き方は基本的に縦書きで、表書きに「御布施」、下段に施主名を記入します。金額は漢数字で記入するのが伝統的ですが、算用数字も許容されています。白い封筒を使用し、奉書紙での包み方がより丁寧とされています。
お布施を渡す際の重要ポイント:
- 両手で袱紗や小さなお盆に乗せて渡す
- 挨拶とともに「よろしくお願いいたします」などと添える
- 直接手渡しや床に置いて差し出すのは避ける
枕経のお布施は通常、他の儀式と合わせて一括で渡しますが、お車代は当日に別途用意するのがマナーです。金額の相場は全国平均で約47万円とされていますが、地域差が大きいため参考程度にしてください。不安な点があれば、葬儀社や菩提寺に相談しましょう。