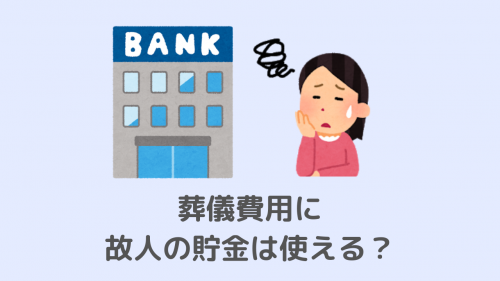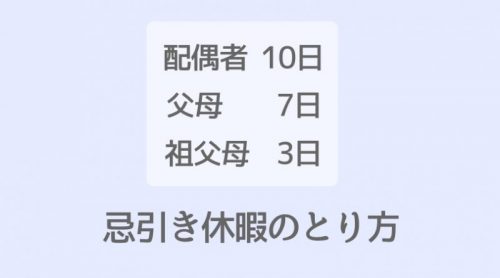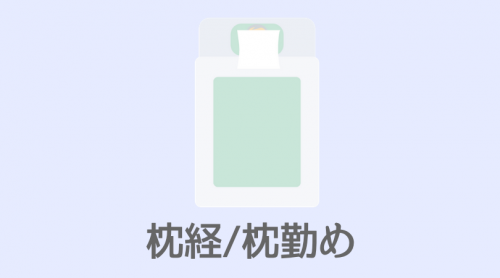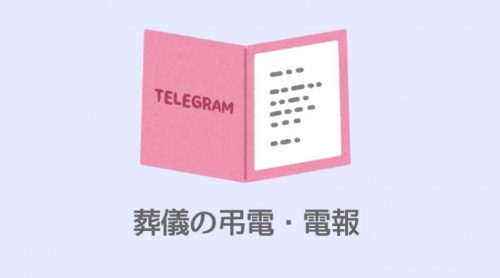国民健康保険や社会保険に加入していた故人の葬儀を行った場合、保険者から給付金(3〜7万円程度)を受け取ることができます。この給付金は葬祭費や埋葬料と呼ばれ、申請しなければ受け取れない重要な制度です。
故人が生前に加入していた保険の種類や、故人と申請者の関係、お住まいの地域などによって給付金の名称や金額が異なります。例えば、国民健康保険の場合は「葬祭費」として多くの自治体で5万円が支給されますが、東京23区では7万円と金額に違いがあります。
最も重要なポイントは以下の3つです:
- 申請期限は死亡日から2年以内である
- 該当の保険者(役所や健康保険組合など)へ申請する必要がある
- 必要書類を揃えて手続きを行う
葬儀社からも助言がもらえる場合がありますが、確実に受け取るためには故人が加入していた保険者に直接確認することをおすすめします。この記事では、2025年最新の給付金制度と申請方法について詳しく解説します。
葬祭費・埋葬料の給付金制度
故人が加入していた健康保険の種類によって、給付金の名称や金額が異なります。これらの給付金は自動的に支給されるものではなく、必ず申請しなければ受け取れませんので、忘れずに手続きしましょう。
国民健康保険:葬祭費
**国民健康保険(国保)**に加入していた方が亡くなった場合に支給される給付金です。主に自営業者や退職者が加入している保険制度です。
給付金の特徴:
- 名称:葬祭費(そうさいひ)
- 給付額:自治体によって異なり、3万円から7万円の範囲
- 一般的な金額:多くの自治体では5万円
- 東京23区の場合:一律7万円
- 申請先:故人が住んでいた市区町村の役所(国民健康保険担当窓口)
市区町村のウェブサイトで「葬祭費」と地域名で検索すると、正確な給付額を確認できます。
後期高齢者医療制度:葬祭費
75歳以上(一部65歳以上で一定の障がいがあり認定を受けた方)が加入する医療制度からの給付金です。
給付金の特徴:
- 名称:葬祭費(そうさいひ)
- 給付額:自治体によって異なり、3万円から7万円の範囲
- 申請先:故人が住んでいた市区町村の役所(後期高齢者医療担当窓口)
国民健康保険と同様に、各自治体のウェブサイトや窓口で正確な給付額を確認できます。
被用者保険の給付金
会社員・公務員など被用者保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合など)に加入していた方の場合の給付金です。故人と申請者の関係によって種類が分かれます。
埋葬料
被保険者本人が亡くなった場合の給付金です。
給付金の特徴:
- 対象:被保険者(本人)が死亡した場合
- 受給者:故人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹など)
- 給付額:一律5万円
- 申請先:協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など(加入していた保険者)
家族埋葬料
被保険者の被扶養者が亡くなった場合の給付金です。
給付金の特徴:
- 対象:被保険者の被扶養者(配偶者や子など)が死亡した場合
- 受給者:被保険者本人
- 給付額:一律5万円
- 申請先:協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など(加入していた保険者)
埋葬費
上記の受給資格がない場合の給付金です。
給付金の特徴:
- 対象:埋葬料を受け取る資格のある遺族がいない場合
- 受給者:実際に埋葬を行った人(親戚や知人など)
- 給付額:実費支給(上限5万円)
- 申請先:協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など(加入していた保険者)
付加給付について
一部の健康保険組合や共済組合では、法定給付(5万円)に加えて独自の付加給付が上乗せされる場合があります。金額は組合によって大きく異なります(数万円〜数十万円)ので、故人が加入していた健康保険組合や共済組合に直接確認しましょう。
会社員の方は、勤務先の人事部や総務部に相談すると、申請手続きや付加給付の有無について案内してもらえる場合があります。
葬祭費・埋葬料の申請方法
申請方法は保険の種類によって若干異なりますが、基本的な流れは共通しています。葬儀後の給付金を確実に受け取るため、以下の重要事項を確認しましょう。
申請期限は2年以内
各種給付金の申請期限は、故人が亡くなった日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると時効となり、申請権利が消滅してしまいます。できるだけ早めに手続きを行うことをおすすめします。
葬儀後の様々な手続きと並行して、この給付金申請も忘れずに行いましょう。特に、死亡届や相続関連の手続きなど、市区町村役場に行く機会があれば、同時に確認すると効率的です。
申請先一覧
給付金の申請先は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。以下の適切な窓口で手続きを行いましょう:
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度:故人が住民票を置いていた市区町村の役所
- 協会けんぽ:最寄りの全国健康保険協会支部
- 健康保険組合:各健康保険組合の窓口
- 共済組合:各共済組合の窓口
申請前に電話で確認すると、必要書類や受付時間などがわかり、スムーズに手続きが進みます。多くの窓口では郵送での申請も受け付けているため、遠方の場合は問い合わせてみるとよいでしょう。
申請に必要な書類
申請には以下の書類が必要です。申請先によって若干異なる場合があるため、事前に確認しましょう:
必要書類リスト:
- 支給申請書(申請先の窓口やウェブサイトで入手)
- 亡くなった方の健康保険証(返却)
- 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書のコピー、埋火葬許可証のコピー、戸籍謄本など)
- 葬儀を行ったことを証明する書類(葬儀費用の領収書、会葬御礼のハガキなど)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 申請者の印鑑(認印可の場合が多い)
- 振込先口座情報(通帳やキャッシュカードのコピー)
- マイナンバー関連書類(必要な場合)
書類のコピーは、原則としてA4サイズで準備します。原本が必要な場合は窓口で確認してください。
申請手続きの流れ
申請の基本的な流れは以下のとおりです:
- 必要書類を準備する:上記リストを参考に、漏れがないよう確認しましょう
- 申請先の窓口に書類を提出する:窓口での提出が基本ですが、郵送可能な場合もあります
- 審査・振込:書類審査後、指定口座に給付金が振り込まれます(通常1〜2週間程度)
申請時に不明点があれば、窓口の担当者に質問するとスムーズです。また、申請後は念のため振込予定日を確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
- 葬儀社が立て替えた場合でも申請できますか?
-
はい、申請できます。葬儀社の領収書に申請者の名前が記載されていれば、申請者が費用を負担したとみなされます。ただし、領収書の宛名は必ず申請者本人の名義であることが重要です。葬儀社に依頼する際に、領収書の宛名を確認しておくとスムーズです。
- 会社を通じて申請する場合の流れは?
-
勤務先の人事・総務部門に相談してください。多くの会社では福利厚生の一環として手続きをサポートしています。一般的な流れとしては、会社に死亡の事実を報告し、必要書類(死亡診断書のコピーなど)を提出します。その後、会社が健康保険組合などへの申請手続きを代行してくれる場合が多いです。不明点は勤務先の担当者に確認しましょう。
- 申請をし忘れていた場合はどうすればいいですか?
-
2年以内であれば申請できます。時効成立前であれば、すぐに該当の窓口に相談しましょう。必要書類(死亡診断書のコピー、葬儀の領収書など)を準備して申請手続きを進めてください。時間が経過していても、期限内であれば遡って給付を受けられます。
- 複数の健康保険に加入していた場合はどうなりますか?
-
原則として、主たる保険(優先適用される保険)から給付を受けることになります。例えば、被用者保険(会社の健康保険)と国民健康保険の両方に加入していた場合は、被用者保険が優先されます。ただし、それぞれの保険制度で給付内容や条件が異なる場合もありますので、詳細は各保険者に確認してください。
- 申請後、給付金はいつ頃受け取れますか?
-
一般的に申請書類に不備がなければ、申請から1〜2週間程度で指定した口座に振り込まれます。ただし、申請時期や自治体・保険者によって処理期間は異なります。申請時に窓口で支給予定日を確認しておくと安心です。繁忙期(年度末など)は処理に時間がかかる場合があります。
- 葬祭費・埋葬料以外に受け取れる給付金はありますか?
-
はい、健康保険以外にも以下のような給付金がある場合があります:
死亡に関連する可能性のある給付金:
- 遺族年金(厚生年金や国民年金に加入していた場合)
- 死亡退職金(会社員の場合)
- 生命保険金(個人で加入していた場合)
これらは別途申請が必要ですので、それぞれの窓口に確認しましょう。
- マイナンバーは申請時に必要ですか?
-
2025年現在、多くの自治体や保険者ではマイナンバーの提示が求められます。申請書にマイナンバーを記入する欄がある場合は、故人と申請者双方のマイナンバーが必要になることがあります。マイナンバーカードやマイナンバー通知カードを準備しておくとスムーズです。ただし、具体的な要件は申請先によって異なりますので、事前に確認しておくことをおすすめします。
まとめ
葬祭費・埋葬料の給付金は申請しなければ受け取れません。故人が加入していた保険の種類を確認し、死亡日から2年以内に必ず申請しましょう。
給付金額は保険の種類や地域によって異なり、国民健康保険・後期高齢者医療制度では自治体により3〜7万円、被用者保険(会社の健康保険など)では一律5万円が基本です。申請には故人の健康保険証や葬儀の領収書などが必要になります。
申請書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で指定口座に振り込まれます。不明点は故人が加入していた保険者(市区町村役場や健康保険組合など)に直接問い合わせることをおすすめします。
お葬式にはさまざまな費用がかかりますので、こうした給付金制度を活用して、少しでも経済的負担を軽減しましょう。