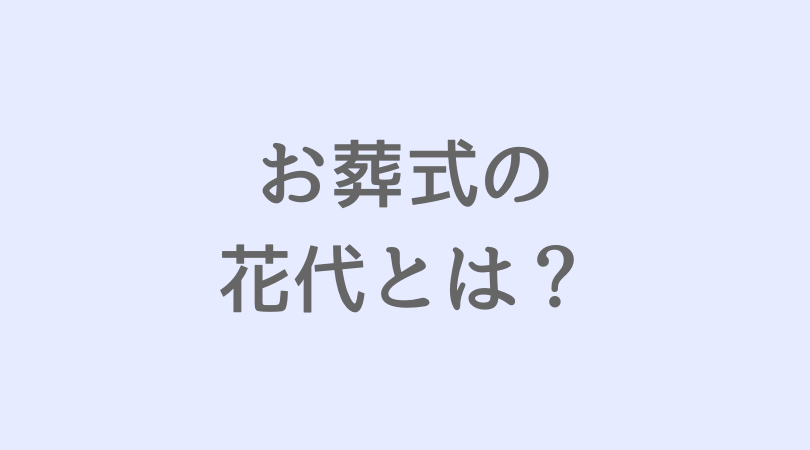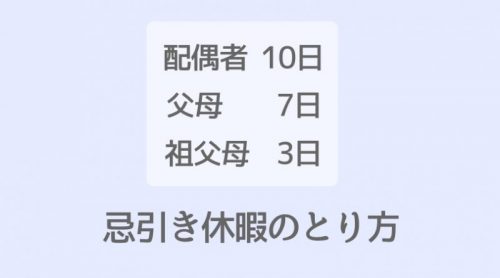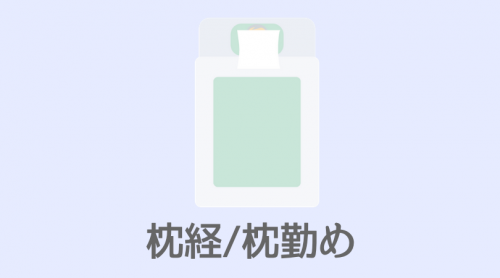葬儀のお花代(はなだい)は、日本の葬儀文化において重要な役割を持つ言葉ですが、実はふたつの異なる意味で使われています。
花代の意味:
- 葬儀や法事で祭壇を飾る生花の代金として業者に支払うもの
- 香典の代わりとして遺族にお渡しするもの
これらは渡す相手や目的が大きく異なるため、状況に合わせた正しい使い分けが必要です。特に近年では家族葬の増加により、香典を辞退されるケースが増え、その代わりとしての花代の重要性が高まっています。
本記事では、花代の基本的な意味から、正しい書き方や包み方のマナー、渡すタイミングまでを詳しく解説します。葬儀に参列する方はもちろん、香典を辞退する家族葬を検討している方にも役立つ情報をまとめました。
葬儀における「花代」とは何か
葬儀のお花代(はなだい)は、日本の葬儀文化において 二つの異なる意味 で使われる言葉です。この違いを理解しておくことで、葬儀の場での適切な対応が可能になります。
花代の2つの意味と使い分け
1. 業者に支払う供花(生花)の代金
これは一般的な意味での花代で、葬儀の祭壇や会場に飾られる供花の代金を指します。供花代金は葬儀の参列者が注文した生花に対して業者(花屋や葬儀社)へ支払うものです。通夜や告別式の開式に間に合うように手配し、一般参列者なら1万円から1万5千円、身内にあたる人なら1万5千円から2万円が相場となります。
2. 香典の代わりとして遺族に渡すお金
特に家族葬などで香典を辞退している場合に、弔意を表すために「お花代」という名目で金銭を包み、遺族に渡すことがあります。これは近年増えている形式で、供物として注文した生花の代金という体裁をとりながら、実質的には香典に近い意味を持ちます。
香典との違いと関係性
香典と花代は、以下の点で明確に区別する必要があります:
支払先の違い:
- 香典:故人の冥福を祈り、葬儀費用の足しにするために遺族へ渡します
- 花代:本来は供花の代金として業者へ支払うものです
準備の仕方: 香典と花代は異なる目的を持つため、別々に準備する必要があります。香典に加えて花代を用意する場合は、それぞれ別の不祝儀袋に包みます。
家族葬での対応: 近年は家族葬が増加し、親族以外からの香典を辞退するケースが増えています。その場合に香典の代わりとして花代を包むことで、弔意を表現できます。親族の葬儀なら3万円から5万円、知人や仕事関係者の葬儀には5千円から1万円程度が相場です。
時代の変化: 葬儀スタイルの多様化により、花代の意味も変化しています。家族葬の普及に伴い、香典を断られる状況が増えているため、花代についての知識も必須となっています。
両者の役割を正しく理解し、状況に応じて適切に準備することで、故人への弔意を正しく表現することができます。
葬儀で仏前へ供える「供花の代金」としての花代
一般的なお葬式では、供物として贈る生花(供花)の代金のことを花代と呼びます。世間的なイメージでもこの意味での花代が先行していることが多いでしょう。
供花の注文タイミングと手配方法
供花を注文するタイミングは:
- 早ければ早いほど良いのが基本原則
- 通夜の開式に間に合うように手配するのが理想的
- 訃報を受けた時点ですぐに手配の準備に取り掛かる
通夜に間に合わない場合の対応策:
- 翌日の告別式に間に合うように手配しておけば問題ない
- 葬儀社や花屋に状況を説明し、最適な対応を相談する
なお、葬儀場によっては業者からの持ち込みがNGとなっている場合もあります。必ず事前に確認してから注文するようにしましょう。
供花代金の相場と立場による違い
供花代金の一般的な相場は立場によって異なります:
一般参列者の場合:
- 1万円から1万5千円程度が標準的な相場
- 故人との関係性によって調整することも可能
故人の身内にあたる人の場合:
- 1万5千円から2万円程度が目安
- より近い関係性であれば金額が上がる傾向にある
花代と香典は別物である理由
香典と花代は明確に区別して考える必要があります:
香典と花代の違い:
- 香典→遺族へ渡す(葬儀代金の足しにしてもらう意味合い)
- 花代→業者へ支払う(供物として注文した生花の代金)
このため、香典と花代は別々に包んで準備する必要があります。香典袋には「御霊前」などと記載し、花代袋には「御花代」と明記して区別します。
葬儀の際に持参する品々としては、香典と花代を別々に用意する必要があることを覚えておきましょう。両方とも弔意を示すためのものですが、受け取る相手と目的が異なるという点が重要です。
香典の代わりとして包む「お花代」の知識
近年増加している家族葬では、親族以外には通知せずに執り行われることが一般的です。このような場合、遺族は参列者からの香典を辞退していることが多く、受け取ってもらえないケースがあります。
香典辞退の場合の選択肢:
- 何も渡さない(マナー違反にはなりません)
- 香典の代わりに供花を贈る
- 祭壇の生花代金という名目でお花代として金銭を包む
香典代わりのお花代は、故人との関係性によって金額が異なります。一般的な相場は以下の通りです。
- 近い親族の葬儀:3万円から5万円
- 知人やお仕事関係者の葬儀:5千円から1万円程度
家族葬の場合は、事前に遺族や葬儀社に香典や花代の受け取り方針を確認しておくことが望ましいでしょう。中には「一切の金品辞退」と明記されているケースもあります。その場合は、葬儀後に弔問やメッセージカードなどで弔意を表すとよいでしょう。
香典辞退でも花代は受け取るというケースも増えています。これは、葬儀に使用する供花の実費という位置づけで受け取るためです。花代として包む場合は、のし袋に「御花代」と表書きすることを忘れないようにしましょう。
家族葬での花代の扱い方には、地域や家庭によって違いがあります。不安な場合は、葬儀社のスタッフに相談するのが確実です。葬儀社では、家族葬における金品の扱いについて経験豊富なアドバイスが得られます。
時代とともに葬儀のスタイルは変化していますが、弔意を表す気持ちは変わりません。香典も花代も、故人を偲び、遺族を気遣う気持ちを形にしたものであることを忘れないようにしましょう。
花代の書き方・包み方の基本マナー
葬儀の花代を渡す際は、適切な袋の選び方から書き方まで、いくつかのマナーを守ることが重要です。
お花代に使用する適切なのし袋と封筒の選び方
お花代を包む袋は、不祝儀袋または白無地の封筒を使用します。選ぶ際のポイント:
- 白無地の封筒:どの宗派でも使用できる万能な選択肢
- 蓮の柄がついた封筒:仏教の葬儀専用なので、神式やキリスト教式では使用不可
- 黒白や銀の水引がついた不祝儀袋:一般的な弔事用として適切
封筒のサイズは、中に入れる金額に合わせて選びましょう。一般的に5千円~2万円程度であれば、標準的な不祝儀袋で十分です。
表書きの正しい書き方
表書きの書き方は宗教や目的によって異なります:
- 仏式の場合:「御花代」と薄墨(灰色の墨)で記入
- 神式の場合:「御花料」と記入
- キリスト教の場合:「献花料」と記入
文字は丁寧に、中央よりやや上部に記入するのがマナーです。筆ペンや万年筆を使用して書くと格調高く見えます。
裏面の記入内容
裏面には以下の情報を記入します:
- 金額:漢数字で記入(例:「壱萬円」「五千円」)
- 送り主の氏名:フルネームで記入
- 住所:省略せずに記入
裏面の記入も薄墨で行います。数字は書き間違いを防ぐため、合計金額の前に「金」をつけると良いでしょう(例:「金壱萬円」)。
宗派別の表書きとマナーの違い
宗派によって表書きやマナーに違いがあります:
- 仏教:「御花代」と表書き。蓮の柄の封筒も使用可能
- 神道(神式):「御花料」と表書き。シンプルな白無地の封筒を使用
- キリスト教:「献花料」または「お花料」と表書き。十字架の柄は避ける
葬儀の花代には、香典のように水引はつけないのが一般的です。また、カジュアルな柄の封筒は不適切なので避けましょう。
表書きがよくわからない場合は、シンプルな白無地の封筒に「御花代」と記載するのが無難な選択です。宗派を確認できる場合は、それぞれの作法に従うと良いでしょう。
花代を渡すタイミングと方法
花代を適切に渡すには、注文ルートや支払先を正確に把握することが重要です。渡し方は主に以下のパターンに分かれます。
葬儀社/花屋へ直接支払う場合
花屋や葬儀社に直接注文した供花の場合、支払い方法には以下の選択肢があります:
- 通夜・告別式当日の支払い: 式に参列した際に葬儀社の事務所で直接支払います
- 後日振込: 業者指定の口座に振り込む方法で、請求書と共に振込先情報が提供されます
- 事前決済: 一部の葬儀社ではクレジットカードやオンライン決済に対応している場合があります
支払い方法は業者によって異なるため、注文時に確認しておくことをおすすめします。不明点があれば葬儀社のスタッフに直接質問することで混乱を避けられます。
喪主経由で注文した場合の渡し方
喪主を通じて注文した場合や、喪主が立て替えている場合は、花代を喪主へ直接渡すことになります。この場合の対応方法:
- 封筒に「御花代」と表書きし、裏面に金額と送り主の名前・住所を記入します
- 通夜か告別式の際に喪主へ手渡しするのが基本的なマナーです
- 親族が代理で受け取る場合もあるため、確実に喪主へ渡るよう伝言を添えましょう
受付での花代の渡し方と伝え方
多くの葬儀では受付が設けられており、そこで花代を渡すことも可能です:
- 香典とは別の封筒に「御花代」と表書きしたものを用意します
- 受付では「これはお花代です。喪主様にお渡しください」と明確に伝えます
- 金額を記入した領収書が必要な場合は、その場で申し出ておくとスムーズです
受付が混雑している場合は、簡潔に用件を伝え、後ろの方を待たせないよう配慮することも大切です。
後日花代を渡す場合のマナーと注意点
やむを得ず後日花代を渡す場合は、以下のポイントに注意しましょう:
- できるだけ早く(葬儀から1週間以内を目安に)渡すのがマナーです
- 直接訪問する場合は事前に連絡を入れ、都合の良い時間を確認します
- 訪問時には「本来なら当日にお渡しすべきところ、遅くなり申し訳ありません」という一言を添えると丁寧です
- 郵送する場合は現金書留を利用し、同封の手紙に経緯を簡潔に説明します
家族葬で参列できなかった場合など、後日花代を香典の代わりとして渡すこともあります。この場合は「御花代」と表書きし、通常の花代と同様に封筒に包みます。
特に香典辞退の家族葬では、後日花代として渡すことで弔意を表すことができますが、事前に受け取ってもらえるか確認することをおすすめします。
特殊な「花代」の種類と対応方法
葬儀や法事において、一般的な供花の代金以外にも「花代」と呼ばれるものがいくつかあります。それぞれ目的や相場が異なるため、状況に応じた適切な対応が求められます。
枕花(まくらばな)の役割と金額相場
枕花とは、故人が安置されている間、枕元に供えられる花のことです。主な役割は以下の通りです:
枕花の役割と特徴:
- 宗教的な意味合いがある
- 故人が安置されている空間を荘厳にする
- 殺風景な状態を避けるための装飾としての機能も持つ
枕花は主に自宅安置の際に飾られるため、一般の参列者が目にする機会はほとんどありません。そのデザインは簡易的で小さめのものが一般的です。
金額相場は5千円から1万円前後となっています。基本的には遺族が負担する葬儀費用に含まれていますが、別途注文が必要な場合は、故人と近しい関係にあった方が手配するのが一般的です。
枕飾りは宗派や地域によって内容が異なるため、自分で花を用意するよりも葬儀社などのプロに依頼する方が安心です。
花輪(はなわ)の手配と金額相場
花輪は葬儀会場の入り口付近に設置される大きな弔事用の飾りで、これを「花代」と呼ぶ地域もあります。
花輪の特徴と変遷:
- かつては生花を使って一基ずつ手作りされていた
- 現在は造花でできたものをレンタルするスタイルが主流
- 個人や団体の名札を付けて飾られる
金額相場は1万円から2万円程度です。供花と同様に、通夜に間に合うように手配するのが望ましく、故人と親しい関係にあった方のものが入り口側に配置されます。
花輪を贈る際の注意点:
- 贈る場合は葬儀社または花屋に早めに連絡する
- 葬儀会場によっては持ち込み不可の場合もあるため事前確認が必要
- 団体で贈る場合は代表者が窓口となって手配することが一般的
法事での花代の扱い方
法事における花代は、葬儀時とは異なる扱いとなる場合があります。
法事での花代の特徴:
- 葬儀ほど大規模な供花は一般的ではない
- 仏花や盛り花として比較的小ぶりなものを用意することが多い
- 金額相場は3千円から5千円程度が一般的
法事で花代を包む場合は、表書きに「御仏前」や「御花料」と記載し、弔事用の不祝儀袋または白無地の封筒を使用します。法事の場合も宗派によって表書きの表現が異なることがあるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
法事に参列できない場合に花代を送る際は、事前に連絡した上で、法要の1週間ほど前に届くよう手配するのがマナーです。
花代の返礼については、法事の場合も葬儀と同様に半返しの考え方で、品物などを返すことが一般的です。ただし地域により習わしが異なる場合もあるため、地元の方に確認するとよいでしょう。
頂いた花代のお返しとマナー
葬儀で頂いたお花代に対しては、適切なお返しをすることがマナーとされています。香典返しと同様に考えるべき部分もありますが、いくつか異なる点もあるため注意が必要です。
花代返しの基本的な考え方
花代のお返しは基本的に香典返しと同様に「半返し」の考え方で行います。頂いた金額の半分程度の価値がある品物を選ぶのが一般的です。ただし、お花代の性質によって対応が異なる場合があります:
- 遺族へ渡された花代(香典代わり)→ 香典返しと同様に返礼品を贈る
- 業者へ直接支払われた供花代金→ お礼状や電話での感謝の意を伝える
お返しの品物選びと相場
花代返しに適した品物の選び方:
- 定番の返礼品:お茶、海苔、タオル、カタログギフトなど
- 金額の目安:頂いた金額の3〜5割程度が適切
- 宗教的な配慮:特定の宗教や宗派がある場合は、その教えに沿った品物を選ぶ
花代の金額別のお返し相場:
- 5,000円の花代 → 1,500〜2,500円程度の品物
- 10,000円の花代 → 3,000〜5,000円程度の品物
- 30,000円以上の花代 → 10,000〜15,000円程度の品物
地域による習わしの違い
花代のお返しは地域によって習慣が大きく異なることがあります:
- すぐに返礼する地域:葬儀から1ヶ月〜49日以内に品物を贈る
- 後日返す地域:頂いた家に不幸があったときに供花を贈り返す「花は花で返す」という考え方
- 返礼不要の地域:花代に対して品物での返礼を行わない地域もある
地域の習わしを知るには:
- 地元の年配者や親族に確認する
- 葬儀社のスタッフに相談する
- 近隣の習慣に詳しい人に尋ねる
返礼不要の場合でも行うべきお礼の連絡
花代に「お返し不要」と記載があった場合や、地域の習慣で返礼が不要な場合でも、何らかの形でお礼の意を伝えることは必須です:
- 礼状を送る:簡潔な文面で感謝の気持ちを伝える手紙を送付
- 電話での挨拶:直接電話をかけてお礼を伝える
- 次に会った時の口頭での挨拶:直接会った際に改めて感謝の意を伝える
いずれの場合も、供花や花代を受け取ったことを明確に伝え、故人を偲んでくれたことへの感謝の気持ちを込めるのが大切です。
供花の記録と管理
複数の供花や花代を受け取った場合は、後々のお返しに備えて記録を残しておくことをおすすめします:
- 葬儀屋から供花の一覧表をもらう
- 開式前に供花や花輪の写真を撮っておく
- 受け取った花代の金額と送り主を控えておく
これらの記録があれば、適切なお返しをスムーズに行うことができます。
よくある質問(FAQ)
香典とお花代を両方渡しても良いか
香典とお花代を両方渡すことは基本的にマナー違反ではありません。ただし、状況によって適切な判断が必要です:
- 一般的な葬儀の場合:香典と供花を別々に準備し、それぞれの目的に応じて渡すことができます
- 家族葬で香典辞退の場合:香典の代わりに花代として包むことが一般的です
- 両方渡す際の注意点:それぞれ別の不祝儀袋に包み、用途を明確にして渡しましょう
渡す際は「こちらは香典、こちらは供花の代金です」と明確に伝えると、受け取る側も混乱しません。
花代の金額の書き方(アラビア数字と漢数字)
花代の金額表記は基本的に漢数字を使用します:
- 表書き:「御花代」と薄墨で記入
- 裏面の金額:漢数字で記入(例:金壱万円、金参千円など)
- 金額の書き方の注意点:
- 改ざん防止のため、「金」の文字を先頭につける
- 大字(壱・弐・参・拾など)を使用する
- 数字の間に余白を空けない
アラビア数字は改ざんしやすいため、不祝儀の場面では使用しないようにしましょう。
お花代を後日渡す場合の挨拶文例
葬儀に参列できなかった場合や後日お花代を渡す場合の挨拶文例:
「この度は〇〇様のご逝去、誠に痛恨の極みでございます。葬儀に参列できず失礼いたしました。故人様のご冥福をお祈りし、ささやかながらお花代としてお納めください。」
後日渡す際の注意点:
- 時期:四十九日法要までに渡すのが望ましい
- 渡し方:直接訪問して渡すか、郵送の場合は必ず書留などの記録が残る方法で送る
- 包み方:通常の葬儀時と同様に不祝儀袋を使用する
家族葬でお花代を辞退された場合の対応
家族葬で香典・花代とも辞退されている場合の適切な対応:
- 基本的な考え方:遺族の意向を尊重し、無理に渡そうとしない
- 代わりにできること:
- 心のこもった弔電を送る
- 後日、故人を偲ぶメッセージカードを送る
- 四十九日や一周忌などの法要の際に供物を贈る
香典・花代を辞退する家族葬が増えている現代では、金銭以外の方法で弔意を示すことも大切です。相手の気持ちを第一に考え、無理に渡すことでかえって負担をかけないよう配慮しましょう。
まとめ
葬儀の花代には「供花の代金」と「香典の代わり」という二つの重要な意味があります。適切に対応するためのポイントをまとめました:
花代の基本:花代は祭壇に飾られる供花への支払いか、家族葬などで香典を辞退された場合の代替品として渡すものです。金額の相場は親族関係で3万円〜5万円、知人や仕事関係者には5千円〜1万5千円程度が一般的です。
書き方と包み方:不祝儀袋または白無地の封筒を使用し、表書きには「御花代」と薄墨で記入します。裏面には漢数字で金額と送り主の名前・住所を記載します。宗派によって表書きが異なる点に注意しましょう。
渡し方のマナー:供花を直接注文した場合は業者に支払い、喪主が立て替えている場合は喪主へ渡します。家族葬で香典辞退の場合でも花代なら受け取ってもらえることもあります。
お返しについて:花代へのお返しは香典返しと同様に半返しが基本です。返礼不要と申し出があっても、受け取ったことを伝える礼状や電話での連絡は必要です。
葬儀の形式や規模が変化している現代では、香典辞退の家族葬が増えています。そのような状況でも、花代を通じて弔意を表すことができるため、適切なマナーを心得ておくことが大切です。ただし、花代も辞退されている場合は、遺族の意向を尊重し、他の方法で弔意を表すことを検討しましょう。