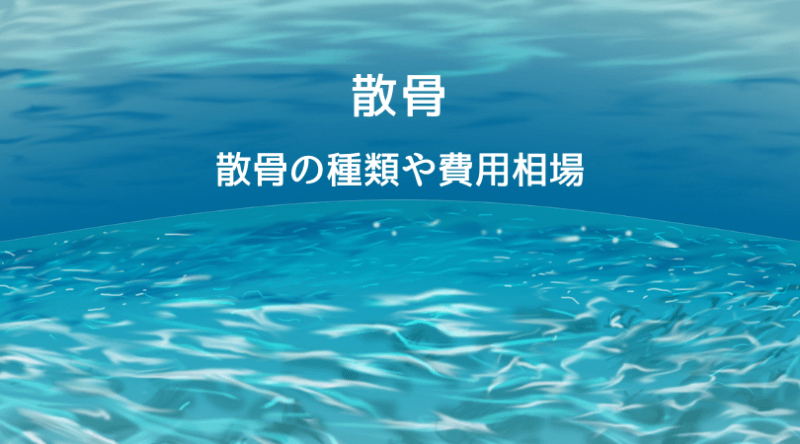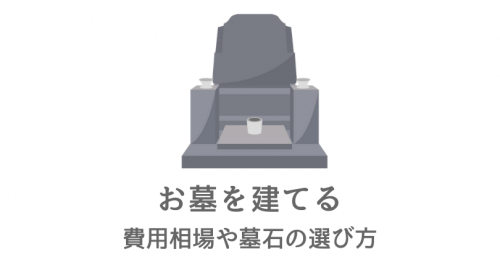近年注目されている埋葬方法のひとつである散骨。自然に還れることと費用面での経済性から、選択肢として検討される方が増えています。散骨の費用相場は2.5万円から30万円程度と幅広く、どのような方法を選ぶかによって大きく変わります。
散骨は、海や山などの自然の中に遺骨を撒く方法で、従来のお墓の購入や維持管理費と比較すると経済的です。また、遺族にお墓参りの負担をかけないという側面も支持されています。
この記事では、散骨の費用相場を中心に、種類別の費用比較、自分で行う場合と業者に依頼する場合の違い、散骨の基本情報や法的な側面まで、散骨に関する疑問を徹底解説します。散骨を検討されている方にとって、適切な選択をするための情報となれば幸いです。
散骨を選ぶ主な理由:
- 自然に還れるという環境への配慮
- お墓の購入・管理費用が不要で経済的
- 遺族にお墓参りの負担をかけたくない
- 思い出の場所で永眠したい
- 寺院との付き合いに煩わしさを感じる
最新の調査によると、散骨に対して好感的な印象を持つ人は全体の3割程度ですが、「他人がするのは構わない」という人を含めると、8割以上の人は散骨に反対していない状況です。時代の変化とともに、自然葬としての散骨への理解と需要が高まっていることがわかります。
散骨の費用相場|2.5万円〜30万円
散骨は従来のお墓と比べて比較的低コストな供養方法として注目されています。最新の相場情報によると、散骨にかかる費用は種類や方法によって2.5万円から30万円程度と幅広く、どのような方法を選ぶかによって大きく変わります。
散骨の種類別費用比較
散骨方法ごとの費用相場は以下のとおりです:
海洋散骨(代行タイプ):
- 業者に全て任せる「委託散骨/代理散骨」:3.5万円〜10万円
- 複数の家族が同じ船に乗り合わせる「合同散骨」:10万円〜20万円
- 1家族だけで行う「貸切散骨/チャーター散骨」:15万円〜40万円
山・里山散骨:
- 一般的な相場:10万円〜20万円
- 海洋散骨と比べて船のチャーター料が不要なため、やや安価
宇宙葬:
- 少量の遺灰を宇宙に送る特殊な散骨:50万円〜800万円
自分で行う散骨:
- 基本的な費用:0円〜5万円(粉骨機材費と交通費のみ)
実際の費用は選ぶプランの内容や地域によっても異なるため、複数の業者に見積もりを依頼することをおすすめします。
散骨費用を決める5つの要素
散骨費用を左右する主な要因は以下の5つです:
- 散骨の方法:
- 業者に全て任せる代行方式が最も安価
- 家族が立ち会う場合は船や会場の手配が必要となり費用増加
- 参加人数:
- 多人数で参加する場合、より大きな船舶や広い会場が必要
- 1人当たりの費用は、合同散骨のように複数家族で分担すると抑えられる
- 散骨の場所:
- 遠方での散骨は交通費や船舶の移動費用が加算
- 地元の港から出航する場合と比べて高額になる傾向
- サービス内容:
- 基本プランに含まれるもの:粉骨、散骨、献花・献酒、散骨証明書
- オプションサービス:プロカメラマンによる撮影、会食、生花祭壇など
- 粉骨の有無:
- 既に粉骨済みか、業者に依頼するかで費用が変動
- 粉骨のみのサービスは約5,000円〜3万円程度
これらの要素を考慮して、自分に合った散骨方法と予算を検討することが重要です。
地域別の散骨費用の違い
散骨費用は地域によっても差があります:
都市部(東京・横浜・大阪など):
- 港湾使用料や船舶維持費が高いため、やや高額な傾向
- 競争も激しいため、サービス内容が充実している場合が多い
地方エリア:
- 港湾使用料が安く、比較的リーズナブル
- ただし、対応可能な業者が少ないため選択肢は限られる
海外での散骨:
- ハワイやグアムなど:30万円〜80万円程度
- 渡航費や現地での手配費用などが加算される
地域による価格差は、サービスの需要と供給バランス、港湾設備の利用料、燃料費などの影響を受けています。
業者に依頼する場合の料金プラン例
実際の散骨業者のプラン例をいくつか紹介します:
基本プラン(代行散骨):
- 料金:2.5万円〜5.5万円
- 内容:粉骨、散骨代行、散骨証明書発行
スタンダードプラン(家族立会い・合同散骨):
- 料金:10万円〜15万円
- 内容:粉骨、船舶チャーター(合同)、献花・献酒、写真撮影、散骨証明書
プレミアムプラン(家族立会い・貸切散骨):
- 料金:20万円〜30万円
- 内容:粉骨、専用船舶チャーター、セレモニー司会、献花・献酒、写真撮影、会食、散骨証明書
多くの業者では、基本料金に含まれるサービスとオプションを明確に区分しています。見積もりを取る際には、追加料金が発生する可能性についても確認しておくことが大切です。例えば、下記のような費用が別途必要になる場合があります:
- 粉骨料金(約5,000円〜3万円)
- 交通費・移動費
- 送迎車両の手配費
- 会食費用
- 特別なセレモニーの実施費用
散骨は一度きりの大切な供養であるため、単に費用の安さだけでなく、信頼できる業者を選ぶことが重要です。価格だけでなく、実績や口コミ、対応の丁寧さなども考慮して選びましょう。
自分で散骨する方法と費用
散骨は業者に依頼するだけでなく、自分自身で行うことも可能です。自分で行う場合の必要経費、準備方法、注意点について詳しく解説します。
自分で散骨する場合の必要経費
自分で散骨を行う場合の費用は、業者に依頼するよりも大幅に抑えることができます。基本的な費用内訳は以下の通りです:
- 粉骨費用: 0円〜3万円程度
- 自分で粉骨する場合は専用の粉砕機が必要(1万円〜5万円)
- 粉骨のみ業者に依頼する場合は1万4千円〜3万円程度
- 交通費: 散骨場所までの移動費(船をチャーターする場合は5万円〜)
- 供養品費: 献花用の花びら、供物などの費用(数千円程度)
- 必要な容器: 水溶性の紙袋など環境に配慮した散骨用の容器(千円〜数千円)
自分ですべてを行う場合、最低限の費用は1万円程度から可能ですが、粉骨を業者に依頼し、船を利用する場合は合計で5万円〜10万円程度になることが一般的です。業者に全てを依頼する場合(10万円〜40万円)と比較すると、かなり費用を抑えることができます。
粉骨の方法と粉骨機の選び方
散骨を行うには、遺骨を2mm以下のパウダー状にする「粉骨」が必要不可欠です。粉骨の方法には以下のようなものがあります:
- 専用の粉骨機を使用する方法
- 小型の粉砕機(1万円〜)や専用の粉骨機(3万円〜)を購入
- 操作は比較的簡単だが、全ての骨を細かく砕くには時間がかかる
- 業者に粉骨のみを依頼する方法
- 費用:1万4千円〜3万円程度
- 手作業粉骨(乳鉢と乳棒で丁寧に行う):2万円〜3万円
- 機械粉骨(専用の粉骨機を使用):1万4千円〜2万円
粉骨機を選ぶ際のポイント:
- 粉砕の細かさ:2mm以下にできるか
- 動力と性能:手動か電動か、処理能力はどのくらいか
- 清潔さ:消毒や洗浄がしやすいか
実際には、遺骨を自分で粉骨することは精神的・肉体的に大きな負担となることが多いため、粉骨のみを専門業者に依頼するケースが一般的です。業者に依頼する場合は、証明書の発行や環境に配慮した処理(六価クロムの無害化など)も行ってもらえる利点があります。
自分で散骨する際の注意点とマナー
自分で散骨を行う場合でも、法律やマナーを守ることが重要です。以下の点に注意しましょう:
散骨時の基本マナー:
- 必ず粉骨を行う:遺骨と分からないよう2mm以下のパウダー状にする
- 平服を着用する:喪服は避け、周囲に違和感を与えない服装を選ぶ
- 環境に配慮:水溶性の紙袋や環境に優しい容器を使用する
- 静かに行う:周囲の人に配慮し、目立つセレモニーは避ける
散骨場所の選び方:
- 他人の所有地は避ける:私有地への無断散骨は不法投棄になる可能性
- 公共の場所での注意:観光地、海水浴場、漁場などは避ける
- 水源地は絶対に避ける:飲料水の水源となる場所への散骨は厳禁
- 海洋散骨の場合:沿岸から一定距離(目安として数km)離れた場所で行う
法的な注意点:
- 自治体の条例を確認:一部地域では散骨に関する条例が設けられている
- お墓から遺骨を取り出す場合:改葬許可が必要
- 海外での散骨:国や地域によって規制が異なるため事前確認が必須
自分で散骨を行うメリットは費用だけでなく、故人の思い入れのある場所や家族だけの時間で静かに行えるという点にもあります。しかし、マナーや法律を守り、周囲への配慮を忘れずに行うことが大切です。不安な場合は、まず専門業者に相談してみることをおすすめします。
散骨代行サービスの選び方
散骨を検討する際、自分で行うか代行サービスを利用するかは重要な選択肢です。特に初めての方や、高齢の方は代行サービスの利用が安心できる選択となります。
散骨業者の料金体系と相場
散骨代行サービスの料金は、サービス内容によって大きく異なります。基本的な費用相場は以下の通りです:
- 粉骨から散骨までの完全代行: 約2.5万円〜10万円
- 散骨セレモニーへの参加: 約10万円〜15万円
- 個別・プライベート散骨: 約15万円〜30万円
- 海外での散骨(ハワイなど): 約30万円〜50万円
料金を決める主な要素:
- 散骨場所(近海か遠方か)
- 参加人数(家族のみか、親族・友人も含むか)
- セレモニーの内容(シンプルか、追加オプションがあるか)
- 船の貸切か共同利用か(プライベート性の高さ)
近年では、リーズナブルな散骨プランも増えており、単に遺骨を送付して代行してもらうだけのシンプルなサービスなら2.5万円前後から利用可能です。一方、思い出に残るセレモニーを希望する場合は、10万円以上の予算を考えておくと良いでしょう。
業者選びで確認すべきポイント
信頼できる散骨業者を選ぶためには、以下のポイントを必ず確認しましょう:
業者選びのチェックポイント:
- 実績と経験(創業年数や実績数)
- 明確な料金体系(追加料金がないか)
- 散骨場所の選択肢(希望の場所に対応しているか)
- 散骨証明書の発行有無
- 散骨後のフォロー(メモリアルクルーズなどのサービス)
- 粉骨の方法(パウダー状にする技術)
- 口コミや評判(実際の利用者の声)
特に重要なのは散骨証明書です。これにより、適切に散骨が行われたことの証明になります。また、散骨後のケアとして、定期的に散骨場所を訪れるメモリアルクルーズを実施している業者もあります。
実際に依頼する前には、複数の業者から資料を取り寄せて比較検討することをおすすめします。多くの業者は無料で資料請求に対応しています。
お布施が必要なケースと相場
散骨の際に宗教的な儀式を行う場合、お布施が必要になることがあります。
お布施に関する基本情報:
- 僧侶同伴の散骨:約3万円〜10万円のお布施が必要
- 宗派による違い:宗派によってお布施の相場が異なる
- 読経の有無:読経を行う場合は必要
- 事前確認:散骨業者に含まれているか確認が必要
実際のお布施は、散骨業者のプランに含まれている場合と別途必要な場合があります。海洋散骨の場合、船上で僧侶が読経するケースが多く、その場合はお布施を準備しておく必要があります。
なお、特定の宗教にこだわらない場合や無宗教の散骨を選択すれば、お布施は不要です。散骨業者に申し込む際に、宗教的な儀式の要否と費用について必ず確認しましょう。
散骨代行サービスの選択は、故人の希望と予算、そして遺族の希望のバランスを考慮することが大切です。多くの選択肢があるからこそ、事前の情報収集と比較検討が重要になります。
散骨とは|基本情報と特徴
散骨とは、火葬後の遺骨を粉末状にして自然の中に撒く埋葬方法です。従来の墓石を使った埋葬とは異なり、故人を自然に還す形で供養する方法として注目されています。近年では環境への配慮や維持費の節約などの理由から、選択肢の一つとして広く認知されるようになりました。
散骨の歴史と広がり
日本における散骨の始まりは比較的新しく、1991年に「葬送の自由をすすめる会」が相模灘で初めての海洋散骨を実施したことが大きな転機となりました。それまでの日本では「亡くなったら墓に入る」という考え方が一般的でしたが、この出来事をきっかけに散骨という選択肢が徐々に社会に受け入れられるようになりました。
第一生命経済研究所の調査によると、散骨について「葬法としては好ましくない」と考える人は全体の約15%に過ぎず、「自分はしたくないが、他人がするのは構わない」という人が55%以上を占めていました。つまり、全体の8割以上の人々が散骨に対して否定的な考えを持っていないという結果が出ています。これは、葬送の多様化が社会に浸透してきた証とも言えるでしょう。
現在では、海洋散骨を中心に、山や樹木の下、さらには宇宙など、様々な場所への散骨が行われています。特に海洋散骨は、広々とした海に還るというイメージから人気となっており、専門の業者も増加しています。
散骨を選ぶ主な理由と特徴
人々が散骨を選ぶ理由は多岐にわたりますが、主な理由としては以下が挙げられます:
散骨を選ぶ主な理由:
- 自然に還れるという考え方に共感できる
- お墓参りで家族に負担をかけたくないという配慮がある
- 費用負担が比較的軽いため経済的な理由から選択される
- 思い出の場所で永眠したいという願いを叶えられる
- 寺院との付き合いなど宗教的な制約から解放される
散骨の最大の特徴は、墓石を必要としない点です。そのため、墓地の購入費や墓石の建立費、さらには年間の管理費など、従来の埋葬方法と比べて費用を大幅に抑えられることが多くの人に支持されています。
また、少子高齢化や核家族化が進む現代社会において、「墓守の不在」という問題も散骨選択の背景にあります。子どもがいない、あるいは子どもが遠方に住んでいるなどの理由から、将来的に墓の管理が困難になることを懸念して散骨を選ぶケースも増えています。
さらに、自分らしい最期を迎えたいという個人主義的な価値観の広がりも、散骨という選択肢が増えている理由の一つです。生前に自分の葬送方法を決めておくことで、残された家族の負担を減らすと同時に、自分の意思を尊重した形で見送られることを望む人が増えているのです。
散骨は従来の墓地埋葬と比較して柔軟性が高く、個人の価値観や希望に合わせた選択ができる点が現代のライフスタイルに適合していると言えるでしょう。
散骨できる場所の種類と特徴
散骨は自然に還る供養方法として年々注目を集めています。ここでは、散骨できる場所とそれぞれの特徴について詳しく解説します。
海洋散骨|最も一般的な散骨方法
海洋散骨は散骨の中で最も人気があり、広く選ばれている方法です。1991年に「葬送の自由をすすめる会」が相模灘で初めて行って以来、多くの人に受け入れられるようになりました。
海洋散骨の特徴:
- 手続きの簡便さ:墓地のような煩雑な手続きが不要
- 費用の安さ:お墓を建てるより経済的(代理散骨なら3.5万円〜10万円程度)
- セレモニーの充実:単に散骨するだけでなく、献花や鐘を鳴らすなど丁寧な儀式が行われる
海であればどこでも散骨できるわけではありません。適切な散骨場所については以下のポイントに注意が必要です:
- 沿岸から一定以上離れた沖合で行う
- 漁場や養殖場、海水浴場、観光スポット付近は避ける
- 専用の船で行くことが一般的(観光船や釣り船からの散骨は不可)
2025年現在、東京湾、相模湾、伊勢湾、大阪湾など日本全国の主要海域で散骨サービスが提供されています。特に東京近郊では羽田沖が人気の散骨スポットとなっており、羽田空港から散骨場所を見て手を合わせることができるという利点があります。
また、散骨後の供養も考慮されており、年に数回散骨場所を訪れるメモリアルクルーズなども行われています。海洋散骨は「撒いて終わり」ではなく、継続的に供養できる仕組みが整っています。
山への散骨|可能な場所と条件
山や森林への散骨(山林散骨)も自然に還りたいという方に選ばれていますが、海洋散骨と比べると実施できる場所に制限があります。
山林散骨の重要なポイント:
- 所有権の問題:山には必ず所有者がいるため、無断で散骨することはできない
- 許可が必要:散骨するには所有者の許可が必須
- 法的制限:国有地への散骨は基本的に違法ではないが、地域によっては規制がある
現在、山林散骨が可能な場所は主に以下の通りです:
- 散骨目的で管理されている私有地
- NPO法人などが所有する散骨専用の山(「葬送の自由をすすめる会」所有の山など)
- 自分の所有地(ただし、穴を掘って埋めるなどの行為は違法)
山林散骨は、山の奥深くで行われることが多いため、個人で行うより業者に代行してもらうケースが一般的です。「山に還りたい」という希望を持つ方には、山林散骨の他に樹木葬という選択肢もあります。樹木葬は墓石の代わりに樹木を墓標とする方法で、里山型の樹木葬なら自然の中に眠るという希望に近い形で供養できます。
宇宙葬など特殊な散骨方法と費用
通常の散骨方法以外にも、個性的な散骨方法が登場しています。その代表が宇宙葬です。
宇宙葬の主な種類:
- ロケット宇宙葬:遺骨をカプセルに入れて人工衛星に搭載し宇宙を旅する(100万円以上)
- バルーン宇宙葬:遺骨をカプセルに入れてバルーンで成層圏まで飛ばす(8〜30万円)
- 月面着陸:月の表面に遺骨を運ぶプラン(数百万円)
その他にも空からの散骨を行う**空葬(空中散骨)**があります。これはヘリコプターや小型飛行機を使って上空から散骨するもので、費用は約30万円からとなっています。ただし、人家のある生活圏から離れた場所でのみ許可されるため、多くは自宅や故郷の上空を旋回してから適切な場所で散骨を行います。
特殊な散骨方法は費用が高額になりがちですが、「宇宙に行きたかった」など故人の夢や希望を叶える形で供養できるという大きな意味があります。選択肢が増えることで、それぞれの人生に合った最期の旅立ち方を選ぶことができるようになっています。
散骨の場所を選ぶ際には、法律やマナーを守ることはもちろん、故人の希望や遺族の思い、アクセスのしやすさなども含めて総合的に検討することが大切です。
散骨に関する法律と手続き
散骨は違法?法的な位置づけ
現在、散骨を直接規制する法律や規定は存在しません。散骨に関連する法律としては「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」がありますが、この法律には散骨に関する記述は一切含まれていません。そのため、法律上は「散骨が存在しない」状態となっています。
厚生労働省は「墓地、埋葬等に関する法律においてこれを禁止する規定はない」という見解を示しており、法務省も「宗教上の感情を害さない限り刑法上の問題はない」「節度を持って行われる限り問題ない」としています。
注意すべき点として、遺骨をそのままの状態で散骨すると「死体遺棄罪」に該当する可能性があります。そのため、必ず遺骨を2mm以下のパウダー状に粉骨することが重要です。
2021年3月30日には厚生労働省が「散骨に関するガイドライン」を公式ホームページに掲載し、散骨が文化として認められる状況となっています。
散骨に必要な許可や手続き
全国的に見ると、散骨には基本的に許可や公的な手続きは必要ありません。行政機関に対する申請書類や届出も存在しません。ただし、以下の点に注意が必要です:
- 墓地や納骨堂から遺骨を取り出す場合の手続き:
- 通常の改葬(墓地から墓地への移動)では「改葬許可証」が必要
- 散骨の場合は自治体によって取扱いが異なる
- 多くの自治体では「移転先なし」として特別な手続きは不要
- 一部のお寺では改葬許可証の提出を求められることもある
- 散骨業者に依頼する場合:
- 遺骨の身元確認のため「埋葬許可証」の提出が求められることが多い
- 業者によっては「改葬許可証」も必要となる場合がある
- 地方自治体の条例:
- 一部の自治体では散骨に関する条例を制定
- 例えば静岡県熱海市では「海洋散骨事業ガイドライン」があり、市の土地から10km以上離れた海上でのみ散骨を行うよう定めている
- 主に事業者向けの規制だが、個人の散骨に関する規定がある場合もある
散骨を計画する際は、実施予定の地域の自治体に事前確認することをお勧めします。
散骨時のマナーと注意点
散骨は法律で規制されていなくても、社会的なマナーや配慮が非常に重要です:
- 遺骨の粉骨:必ず2mm以下のパウダー状にすること
- 散骨場所の選定:
- 人が多く集まる場所(海水浴場、観光地など)は避ける
- 養殖場などの漁業権がある海域では行わない
- 個人所有の土地で行う場合は所有者の許可が必要
- 適切な服装:
- 喪服ではなく普段着で行う(喪服姿での散骨は周囲に不快感を与える可能性がある)
- 時期の配慮:
- 海洋散骨の場合、海水浴やマリンレジャーが盛んな夏期は避ける
- 天候と自然環境への配慮:
- 強風時は避ける(粉骨した遺灰が風で飛ばされる)
- 自然環境を汚さない(花なども生分解性のものを使用)
散骨後のことも考慮し、供養の方法や手を合わせる場所についても事前に考えておくとよいでしょう。一部の海洋散骨サービスでは、散骨した場所を訪れるメモリアルクルーズなども提供しています。
散骨は「自然に還る」という考え方に基づく供養方法ですが、他者の宗教観や感情を尊重し、社会的な理解を得られるよう節度を持って行うことが大切です。
散骨後の供養方法
散骨は「手を合わせる場所がなくなる」というイメージがありますが、実際には様々な供養方法があります。お墓参りのように故人を偲ぶ場所や方法を持つことは、残された家族にとって大切な心の整理の時間となります。
散骨場所への訪問方法
メモリアルクルーズは散骨後の最も一般的な供養方法の一つです。これは散骨した海域に再び船で訪れ、故人を偲ぶセレモニーを行うサービスです。多くの散骨業者がこのサービスを提供しており、一周忌や三回忌などの節目に利用する方が増えています。
メモリアルクルーズには主に二つの形式があります:
- チャーター便(個別訪問): 散骨した正確な緯度・経度の場所まで家族だけで訪れるプラン。日程や訪問先を自由に設定できる利点がありますが、船1隻分のチャーター料(通常5万円〜15万円程度)が必要です。
- 合同クルーズ(共同訪問): 複数の家族が一緒に参加する形式で、費用を抑えられます(一人あたり1万円〜3万円程度)。各家族が散骨した場所を順番に訪れる場合と、散骨海域の近くで合同で供養を行う場合があります。
羽田沖などの散骨では、陸地からの眺望供養も可能です。羽田空港や周辺の展望スポットから散骨した海域を眺めながら手を合わせることができます。
散骨後の供養に関するオプションサービス
散骨後も故人とのつながりを感じられる様々な供養オプションが登場しています:
分骨による手元供養は、散骨前に少量(スプーン1杯程度、約20g)の遺灰を残しておく方法です。専用のミニ骨壷やペンダントなどのアクセサリーに入れて身につけたり、自宅に安置したりできます。
その他の供養方法としては:
- 故人の記念日に散骨場所の方角に向かって手を合わせる
- デジタルメモリアルとしてオンライン上で供養する専用サイトやアプリの利用
- 写真や思い出の品を飾ったメモリアルコーナーを自宅に設ける
- 自然に配慮したお供えとして、生花や自然素材でできた供物を散骨場所に持参する(プラスチックなど分解されない素材は避けましょう)
供養で最も大切なのは形式ではなく**「故人を偲ぶ気持ち」**です。散骨という選択をしても、故人との絆を感じられる方法は数多くあります。家族で相談しながら、自分たちに合った供養の形を見つけることが大切です。
まとめ|散骨は2.5万円からできる自然に還る選択肢
散骨は「自然に還りたい」「お墓参りで家族に負担をかけたくない」「費用を抑えたい」といった理由から、近年選択する方が増えています。費用面でも従来のお墓建立と比較して経済的な選択肢となっています。
散骨の種類と費用相場をまとめると:
- 自分で行う散骨:基本的に0円(粉骨費用と交通費のみ)
- 委託・代行散骨:最も安価で2.5万円〜5万円程度
- 合同乗船散骨:複数家族で乗り合いで10万円〜20万円程度
- 貸切乗船散骨:1家族で船をチャーターして15万円〜40万円程度
- 特殊な散骨(宇宙葬など):50万円〜250万円程度
散骨は法律で禁止されていませんが、遺骨を2mm以下に粉砕することや周囲の環境や人に配慮することなど、マナーを守って行うことが重要です。業者を選ぶ際には、実績や口コミ、サービス内容をしっかり確認しましょう。
散骨後の供養方法としては、メモリアルクルーズへの参加や手元供養のためのミニ骨壷の活用など、様々な選択肢があります。自分らしい最期の選択として、また家族に経済的・精神的負担をかけない選択として、散骨は一つの有効な方法と言えるでしょう。
散骨を検討する場合は、家族とよく話し合い、自分や故人の希望に合った方法を選ぶことが大切です。費用だけでなく、供養の形としても納得のいくものを選びましょう。