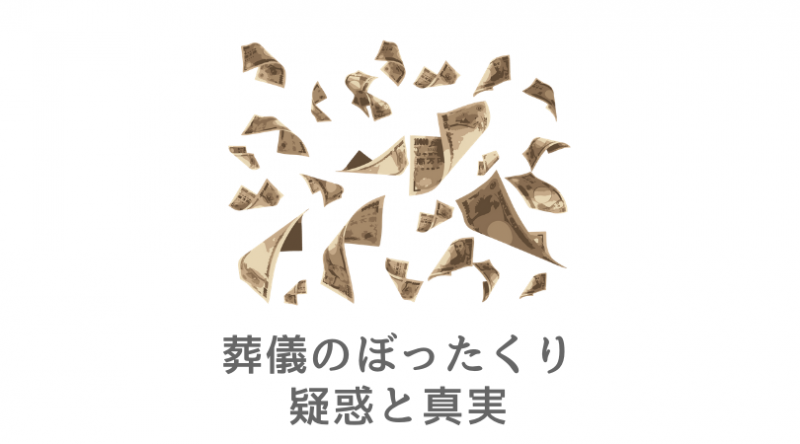葬儀業界の価格がぼったくりではないかとうイメージを持つ人も多いかもしれません。
「そもそも日本の葬儀は海外と比較して高い」という話もありますが、この部分は国内においてはどうしようもありませんのでこの記事では触れません。
ほとんどの場合は、必要なサービスを見極められずに葬儀屋の言いなりになり過剰なサービスを依頼してしまうことと、事前に葬儀社からの説明が不足しており意図しない料金が請求されることの2つの要因から「ぼったくり感」が生まれています。
ぼったくり防止としての結論は、事前に見積もりを出して相場感や予備知識を準備しておくことがベストです。
どういう状況でぼったくられるのか、どんな人がぼったくりに合うのかを知っていただき、適正な料金で葬儀を行うための参考にしていただけると幸いです。
葬儀がぼったくりのイメージがある理由
ぼったくりかな?ぼったくられた?と感じるのは「金額が想定していた幅よりも高くなった場合」です。
思っていたのと比べて高いという時ですね。
ただ、葬儀業界の実態としてはあからさまに法外な金額を請求してきたり、相場からかけ離れた値段設定をしているという意味でのぼったくりはほぼありません。
あってもごく一部の葬儀屋です。
想定より高いと感じる理由は大きく2つのパターン
- 葬儀内容の自動的な質・量のランクアップがなされる
- 事前の説明が不足して喪主に了承を得ていない金額がある
あからさまなボッタクリ価格は無い
葬儀業界においてあからさまに値段設定がおかしいようなボッタクリは基本的にありません。もちろんある程度の差額はありますが。
たとえば、ビールを1本たのんだ場合に、ビール中瓶(通常500円程度)が3000円と請求されるようなぼったくりの仕方は無いということ。
ここ数年間は葬儀関連の価格が公開されるようになり、ある程度は誰でもインターネットで情報を得ることができるようになっています。
また、もし法外な値段を請求した場合は、その情報が個人によって拡散されることも十分に有りえますので、葬儀社としてもいわゆる「ボッタクリ価格」をつけることはなかなか難しいです。
ですので、基本的に現代の葬儀においてぼったくりと感じるのは「内容のランクアップ」と「事前説明不足」のどちらかが原因となってきます。
量・質のランクアップとは
葬儀の費用は内訳を見ると様々な項目が含まれます。
その中で、それぞれ松竹梅のように商品・サービスのランクを選択できます。
棺・着物・お弁当など、最低限必要なものから高級なものまでどれを選ぶかは人それぞれです。
もちろん自ら望んで高級なものを選択する人も大勢いらっしゃいますので、この場合はその分価格が高くなることは仕方がありませんし、喪主としても希望どおり豪華な葬儀にできて満足します。
ただ、意図せずに上のランクのものを選択してしまった場合は、あとから「もっと安くできたのでは?」という不満につながります。
例えば、うなぎ屋の鰻重が松竹梅の3段階があるとして「とりあえず真ん中の竹」にしておきましょうと提案されて了承したとします。
もちろんこの場合は竹の値段でちゃんと竹のサービスが提供してもらえます。
しかし、あとあと全体の半数以上は一番安い梅を選んでいたとわかったりします。こうなると「私も梅でよかったのでは?」となりますよね。
鰻であれば、日本人のほとんどの人が一度以上は食べた経験があるでしょうから、値段とサービスの判断がしやすいです。
しかし、初めての喪主を務める場合には、どのランクにしたら良いかの判断はなかなか難しく、葬儀社の言われるがままに上のランクのものを注文してしまう。
葬儀社としてはなるべく値段が高い葬儀を執り行ったほうが売上につながりますので、わざわざ安い方を勧めないことは理解できると思います。これは葬儀に限らずあらゆるビジネスで同様です。
これが金銭的な不満がでる要因の一つです。
費用に関する説明不足について
葬儀の費用内訳は以下の2つに分けられます。
- 棺や祭壇など事前の打ち合わせで金額が決まるもの
- 食事やお返しの数など当日の状況で変動する費用
親族以外の参列者の数はおおよその目安はあっても、当日にならなければ正確な数を決めることはできません。
そのため、葬儀・告別式の最中に追加でお弁当や返礼品の追加発注を出すことは普通です。
それも、葬儀中は喪主にいちいち了承をとる余裕がありませんので、葬儀社の判断で追加発注を行うことがよくあります。
これは葬儀屋さんとして「事前に葬儀費用を決定できない」という言い分にもなりますし、そうして当日柔軟に対処・調整するのが合理的な判断だと思います。
問題は、そのように「当日、了承を得ずに必要なものを追加発注する可能性がある」ことを事前の打ち合わせ時に説明をして了承を得ていないことです。
事前に「こういう理由で、この部分は急遽追加になる可能性があって、こうだったら予算内でおさまるけども、このくらい金額が増える可能性もある」と説明して了承をもらっているなら金額的に不満はでないわけです。
これを怠って、葬儀を受注するために最低限の料金だけを提示し、総額は終わった後に伝えて請求するような葬儀屋がいるからぼったくりに感じることがあります。
消費者として、事前の説明をしっかりしてくれる葬儀屋を選ぶ必要があります。
ぼったくられる人・ぼったくられるタイミング
料金に不満が出てしまうのは「意図しないランクアップ」と「葬儀屋さんの説明不足」です。
たまたま良心的な葬儀屋さんに当たればいいのですが、無知のまま協力的ではない葬儀屋さんにあたってしまうと足元をみられて意図しないランクのもの、納得のいかない過剰なサービスを買ってしまいます。
このちゃんとした葬儀屋に頼めるかどうかの分かれ道は家族が病院で亡くなったタイミングです。
日本人の7割は病院で亡くなると言われています。
この時点で葬儀に関してなにも決めておらず、病院からの搬送や葬儀の準備を急かされる状態になってしまうと葬儀屋の言いなりとなってしまいます。
病院で亡くなった場合ですが、まず搬送をどうするか決めなければなりません。
ここで決めている葬儀社があれば、搬送を依頼すればいいのですが、そうでない場合は病院と提携している葬儀屋を紹介してもらうか、突然その場に現れる葬儀屋の営業か葬儀屋ブローカーに捕まって依頼することになってしまいます。
依頼人を葬儀屋に紹介する専門の仲介人やブローカーも存在します。
もちろん病院が提携している葬儀屋が全て悪い業者というわけではありません。
ただし、病院で慌てて葬儀屋に依頼するという時点で、自分で葬儀の準備をしていない人ということが確定しています。
そういう人は葬儀について何も決められていませんし、十分な知識も無いと見られますので、足元を見られやすくなるのは当然です。
その時が来てから慌てて判断を求められる状況や、そういった状況になってしまう人が葬儀屋のいいなりになってしまいがちと言えます。
ボッタクリに合わないために出来ること
葬儀が必要になるのは急なことですし、生前に葬儀の話をするのも気がひける部分も確かにあります。
それでもやはり納得がいく葬儀をするために最もいいのは内容をある程度先に決めておくことです。
事前にある程度の知識を身につける
葬儀でぼったくられない、つまり自分が納得の行く葬儀をするために必要なのは事前の準備です。
準備と言っても具体的に細かいことまで決める必要はありません。
葬儀を検討する時に必要な以下。
- 葬儀の場所
- 葬儀の規模(人数など)
- 総額の予算
とりあえずこれだけを決めておくことです。
そしてこれを決めるうえでポイントになるのは家族・親族と事前に相談できることです。
なぜぼったくられるかというと、何も決めていない状態で、病院で時間を急かされ、誰にも相談できずに葬儀屋の言いなりになるからです。
こういった状況下では冷静に正しい判断が出来なくて当然です。
まだ時間に余裕があるのであれば、複数の葬儀社に事前の見積もりを出しておくのがおすすめです。
見積もりを出すことによって、葬儀社によって対応が違うとか、そもそもどんな見積もり項目があるのかなどを事前に知ることができます。
多くの葬儀社は事前相談や見積もりに対応しています。
もちろん、見積もりを出したからと言って必ずその葬儀社に依頼しなければならないということはありません。
見積もりを出す段階でも「危篤なのか」「まだ時間的に十分猶予があっての見積もりなのか」を考慮してくれます。
事前に一度見積もりを出して、その内容をざっと見ておくだけでも、いざという時に正確な判断をする材料として必ず役に立ちます。
全く事前の知識がない状態でその時を迎えて、数時間から半日の間にしっかりと納得のいく葬儀を作れるわけがありません。
今、まだ余裕がある状態であれば2〜3社に見積もり・相談を行い、どんなものなのかざっくりでも見ておくのが懸命です。
ぼったくり業者を見分ける目を持つ
事前知識と別に必要なのが、実際に葬儀社の人間と話す時に相手が言っていることを見極めることです。
細かいところはキリがないので、大枠で判断する時に必要なのは説明不足でないかどうかです。
「当日になってみないとわからない」「皆さんこれを選んでます」など、具体的なことをはぐらかすタイプの葬儀社は怪しいです。
実際に当日終わってみないと確約できないことはたくさんありますが、それでもどういった理由で何がわからないのかを説明することは出来ますし、その方が親切です。
お弁当は5000円くらいで、数量は当日の人を見て決めます。○良い例
お弁当は3000円〜8000円のものを選べます。人数は50人分用意して見込みは○○円ですが、もし当日不足するようなら追加するので、プラス○○円になる可能性があります。
こういった話を事前相談や、当日の打ち合わせで丁寧にしてくれる葬儀社が安心でしょう。
ただ、それでもいざとなったときはなかなか冷静な判断が難しい心境になっていますので、やはり事前に見積りをとって家族・親族と相談しておくことが一番重要だと考えます。
葬儀のぼったくり事情まとめ
ボッタクリの要因は2つ。
- 葬儀社のいいなりでサービスを発注してしまう
- 理解できていない料金が請求される
これを防ぐ方法としては、葬儀社が言っていることを見極めていいなりにならないことです。
わからないことがあればしつこく説明を求めましょう。もし、その説明をはぐらかすような葬儀社であれば他の葬儀社を検討した方が安全かもしれません。
いずれにせよ、葬儀社が適正なサービスを行ってくれるかを判断するためにも事前の見積もりをとって予備知識を入れておくことが非常に重要です。
一度でも見積もりを見たことがある状態、手元に他社の見積もりがある状態で打ち合わせをすることで、いざと言う時に急に目の前に現れた葬儀屋が真っ当なのかどうかを判断する材料になります。